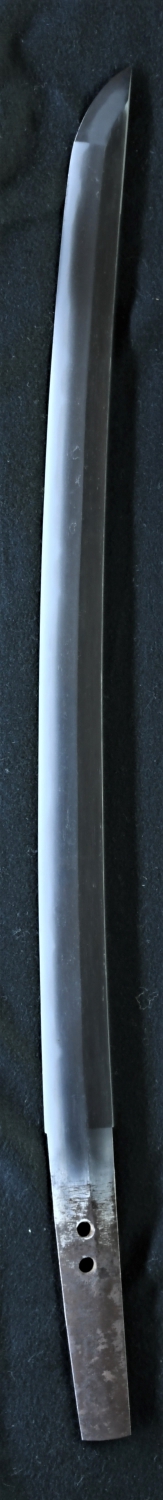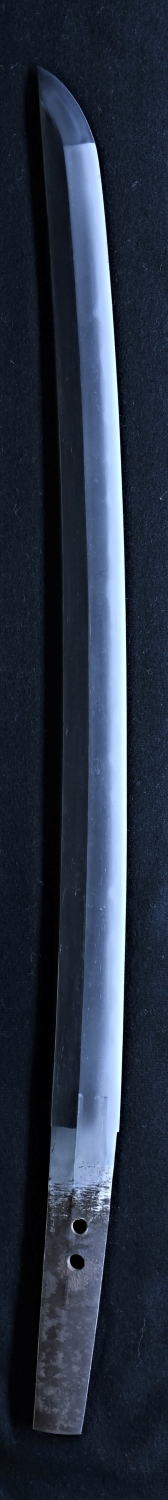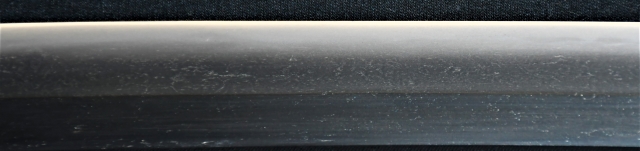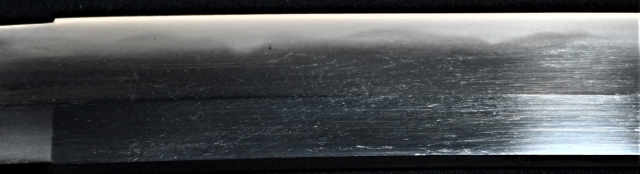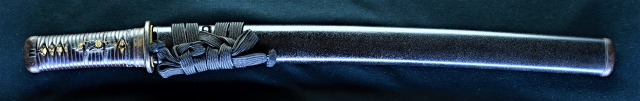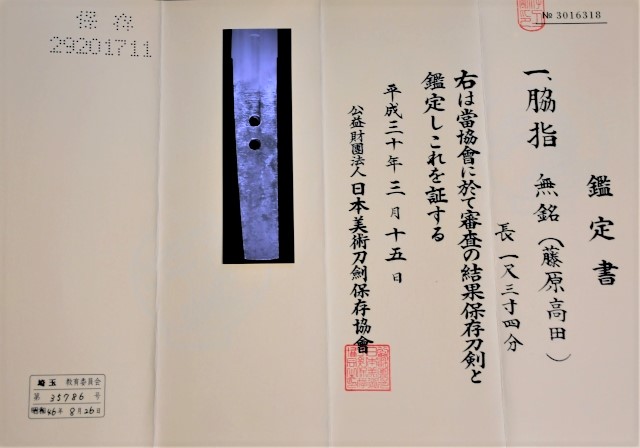詳細画像(藤原高田)
藤原高田と鑑定された脇指をお届けします。時代のあるなかなか綺麗な拵が付属して
います。小柄櫃が空いていましたので、当店で小柄を入れておきました。
九州の豊後国には、古刀の時代から高田と称される刀工集団がありました。古刀時代
はおそらく、豊後を中心に九州北半分を支配した大大名、大友氏領国における需要を
中心に、瀬戸内地域の多くの武士達に渡ったものと思われます。作域は広く、備前刀に
見える物、三原風に見える物もありますし、尖り刃を交ぜて関の刀にも見えそうな物
すらあります。刀工は数百人の存在が分かっており、日本でも有数の大刀工集団だった
と考えられます。この時代の高田鍛冶の多くは「平」姓を名乗っていましたので、
「平高田」と言います。
大友氏が衰退し、関ヶ原の戦に連動した九州動乱の中での再興にも失敗した頃から、
平高田の活動はほぼ止まります。その後、豊臣政権の中では加藤清正の飛び領となって
いた大分近郊の鶴崎港はそのまま、加藤氏の後に肥後を領有した細川氏の領地となり
ますが、その鶴崎港からほど近い高田村を拠点として、再び刀工が刀を鍛え始めます。
今度は、彼らは「藤原」姓を名乗りますので「藤原高田」と呼ばれます。平高田と
同様に、やはり広い作域の刀を、江戸時代を通じて作り続けました。直刃の上出来物
などは、銘を消して肥前刀に紛れさせた物も多いと言われます。斬れ味の良い業物と
されている刀工も何名もおり、古刀時代に引き続いて実用に耐える良い刀を作っていた
ことが分かります。領主である肥後細川家の厚い庇護があったようです。
今回ご紹介する脇指は、日本美術刀剣保存協会から「藤原高田」と鑑定されました。
肥前刀にはあまり出ない映りが立っていること、互の目刃に尖り刃が交じること、鎬が
やや高いように感じられること、帽子が小丸であること等が、藤原高田の特長と考え
られたのかもしれません。磨上げられたなかごの錆色もかなり深く、なかごを切られた
のは江戸時代も早い内なのかと思いました。よい刀身だと思います。
拵はおそらく江戸時代後期のものでしょう。鞘は石目塗、柄は細い革で巻き、目貫を
出して据えてありました。縁頭と鍔は同じ意匠と思われます。すべて鉄地で、そこに
銅と銀などで草花の紋様を象嵌してありました。画像をアップしてみますが、お分かり
になりますか?赤銅の出し目貫も草花図ですし、全部同じデザインで作らせた物で
しょう。端正な拵だと思います。
ます。鞘に若干、当たったへこみはありますが、例えば演武の時に拵だけを大刀の
指添えとして腰にしても良いと思います。皆様のお手元に是非どうぞ。